 |
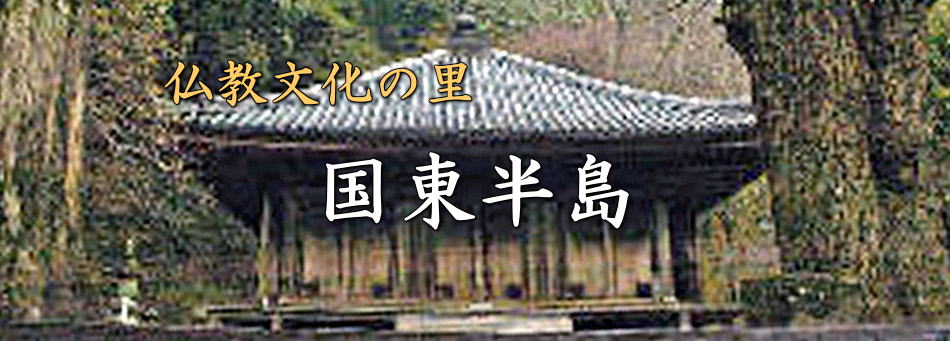 |
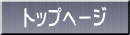 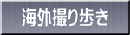 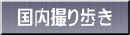 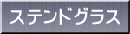  |
| |
終戦後、食糧難の大阪から知人を頼って戦後疎開した先が国東半島の突端にある町、竹田津というところで小学校5年の時だった。東
京に行くまでの約7年間この地で生活した。国東半島には六つの郷(武蔵、来縄、国東、田染、安岐、伊美)に28の寺院が開創され、6万
9千体の仏像を造ったといわれている。国東半島一帯 にある仁聞関連の寺院を総称して「六郷山」または「六郷満山」といっている。平
安時代から仏教が 盛んだったところで今も半島のいたるところに仏教遺跡か見られる。
|
|
|
|
 |

|

|
| 富貴寺大堂(国宝) ,2008年2月撮影 |


| |
天台宗の仏教寺院
本尊は阿弥陀如来、開基は仁聞と伝えられている。
富貴寺大堂は、近畿地方以外に所在する数少ない平安建築の一つとして貴重な存在であり、1952年11月22日に国宝に指定されている。
国東半島の六つの郷(武蔵、来縄、国東、田染、安岐、伊美)に28の寺院を開創し、6万9千体の仏像を造ったといわれている。国東半島一帯にある仁聞関連の寺院を総称して「六郷山」または「六郷満山」といっている。 |
|

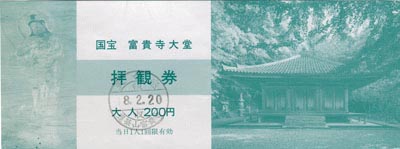 |
 |
 |
 |
 |
| |
本尊の阿弥陀如来坐像は、一体の姿で長年親しまれてきたが、富貴寺本堂の改修に伴って脇侍(わきじ)の観音菩薩と勢至菩薩を伴った「阿弥陀三尊像」(下二段目の写真)の姿で御開帳されています |
 |

| |
富貴寺の国東塔
国東塔は、大分県国東半島を中心に分布する宝塔の一種。基礎と塔身の間に反花または蓮華座、ものによっては双方からなる台座を有するのが外観上の最大の特徴とされる
国東塔の総数は約500基といわれ、その分布は大分県内北部から西部にも及ぶが、約9割が国東半島に集中している
 |
一般の五輪塔 |
|
|
 |
県立歴史博物館で復元展示されている壁画 |
|
| 磨崖仏 ,2008年2月撮影 |
| |
|
| |
熊野神社(熊野権現)へ至る300mの山道と鬼が一夜で築いたという伝説の石段を上った左手の岩盤に彫られたのが熊野磨崖仏。藤原末期の作と推定され国の重要文化財に指定されている。 |
|
 |
| |
  |
| 真木大堂 ,2008年2月撮影 |
木造阿弥陀如来坐像
 |
| |
真木大堂
真木大堂は、馬城山伝乗寺の堂宇のひとつであったと伝えられる。伝乗寺は、養老2年(718年)に仁聞菩薩によって開創されたと伝えられる六郷満山の本山本寺8ヶ寺のひとつで、その中でも七堂伽藍を有する最大規模の中心的寺院であり、田染地区に36の寺坊を有していたという。しかし、約700年前に火災により焼失し、詳細な史料は残されていない
現存するのは、江戸時代に再建された小規模な旧本堂(大堂)と、昭和40年代に新造された収蔵庫のみである[1][2][3]。真木大堂に収められている国の重要文化財の4件9躯の仏像は、伝乗寺の各堂宇に伝えられたものが、各寺坊の衰退に伴って一箇所に集められたものだとされる。
ウィキペディア(Wikipedia)引用 |
 |

木造不動明王二童子立像
木彫の不動明王では国内最大級のスケール |

木造大威徳明王像(上2枚)
白牛に跨がる六面六臂六足の像。大威徳明王像としては日本最大 |
| 川中不動(磨崖仏) ,2008年2月撮影 |
 |
| |
「長岩屋川」の中にある大岩に刻まれている摩崖仏が「川中不動」の通称で知られるもの。
室町時代に、氾濫を繰り返す川の水害防除の願のために造られたと伝えられています。寺伝によれば養老天念寺(下の写真)は山号は長岩屋山という天台宗の寺院で、 六郷満山の中山本寺で、寺伝によれば養老2年(718年)に仁聞により創建されたとされています。
平安・鎌倉時代には修厳と祈願の寺院として栄えていた。本堂と庫裡は昭和16年の集中豪雨で流出してしまい、現在は講堂と六所権現が残るのみとなっている。 |
|
 |

天念寺 |
 |
 |
 |
| copyright©2022:yoshitoworld; all rights reserved |